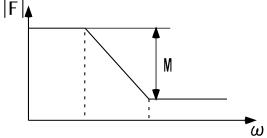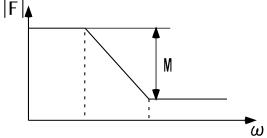2.2 LF(Loop Filter)
LFはローパスフィルタの役割を持ち、PDからの位相差出力
をVCOの制御電圧に変換する
役割を持ちます。つまり、PDから出力されたPWMの方形波を直流に近い形の信号に変換します。
つまり、デューティ比が大きいほど電圧は高くなります。
LFはPLLのコントローラに相当する要素であり、
その設計をしっかり吟味しないと望みどおりの特性を得ることはできません。
(設計方法については、古典的PLL-ICの4046Bの設計例で別に示します。)
PLLのLFはローパスフィルタであると言っても一般には1次(あるいは2次)の低い次数のフィルタを
用います。
ここでは、下左図の簡単なパッシブ・リード・ラグフィルタの
場合を紹介します。
下右図はその周波数応答ですが、なぜローパスフィルタでありながら、
高周波域でもう
一度平坦に戻すかというと、高周波域で位相が回り過ぎないように戻している(リード)のです。

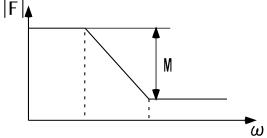
LFの周波数応答は上右図のとおりなのですが、これだけでは面白くないので、
実際にPLLを設計した場合にどのような入出力波形になるかを下のグラフで示します。
ここで、
M:減衰度[dB]
TL:PLLのロックイン時間[sec]
(PLLの応答速度を表す)
duty:デューティ比[%]
です。
では試してみましょう。
- Mを(負の方向に)小さく(-5など)
していくと波形が方形波に近づいていってしまい、
逆にMを(負の方向に大きく)していくと
-50をこえたあたりからほとんど
変化しなくなります。これは、Mは減衰度を表しているためで、
Mが大きくなると高周波の出力が影響しないほど小さくなるからです。
- TLを大きく(リロードしてTL=0.03など)していくと波形はきれいになるが、
ロックイン時間が遅くなるため出力が小さくなってしまいます。
逆にTLを小さく(TL=0.005など)していくとロックイン時間が
早くなるので出力は得られるようになるが、波形が汚く(ジッタ)なってしまいます。
次は、このLFの出力波形で駆動されるVCO(電圧制御発振器)を調べます。
<<BACK NEXT>>